
スーパースポーツの技術は
他のジャンルに転用される
各メーカーのフラッグシップという役割も担うことが多いスーパースポーツには、その時代における最先端の技術が多数投入されている。それらは、スーパースポーツモデルでの採用を経て、他のジャンルでも使われることが多くある。
過去を考えてみると、スーパースポーツのパワーユニットを使った運動性能重視のネイキッドというのは数多くある。なかには、スーパースポーツのカウルをはぎ取ってネイキッド化した機種も存在する。とはいえそのようにエンジンや車体を丸ごとという転用では、スーパースポーツで培われた技術を享受できるジャンルや排気量帯は限られてしまう。
しかし、そればかりではない。制御技術や機構の一部を、スポーツ系以外の機種に流用した例は、これまでもたくさんあるのだ。いまのスーパースポーツに使われている最新技術も、いずれはスタンダードな技術として多くの機種に使われるかも!?

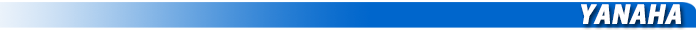
ヤマハも、SSで使われた技術を他のマシンカテゴリーで積極的に転用している。06年型のYZF-R6は量産二輪車初の電子制御スロットル(YCC-T)を採用し、また翌年のYZF-R1は吸気管長が可変するYCC-Iというシステムを初搭載したが、これらの技術は怒涛の加速感を追求した2代目VMAXでも使われている。

カワサキは、11年型のニンジャZX-10Rで、モトGPマシンの技術を使った予測型レースタイプのトラクションコントロールシステムとなるS-KTRCを採用。翌年型のニンジャZX-14Rでは、安全を重視した従来のKTRCに、速く走るために開発されたS-KTRCの技術を加えた、より制御能力が高い3モードKTRCへと昇華させた。

旗艦SSのS1000RRをさらに発展させたHP4(日本では12年12月に発売開始)は、量産二輪車では世界で初めて、アクティブサスペンションであるDDCを搭載。この機構は、翌年に登場したネイキッドのS1000R、さらに15年型でモデルチェンジが施されたS1000RRに採用された。今後も、転用機種の拡大が予想される。