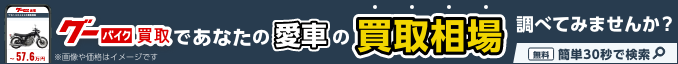バイクの排気量とは?総排気量で異なるメリット・デメリットも紹介
これからバイクに乗りたい、バイクの免許を取得したいと考えている方のなかには、総排気量(排気量)について知りたいという方もいると思います。
総排気量には、大きく分けて5つの種類があり、総排気量ごとに異なる運転免許が必要です。さらに、総排気量が変わることでメリット・デメリットもあるため、ニーズやライフスタイルに合わせてバイクを選ぶようにしましょう。
そこで今回は、バイクの総排気量とは何かという点に加えて、総排気量別のメリット・デメリット、総排気量によって異なる運転免許や維持費などについて解説していきます。
バイクの排気量とは?
バイクの排気量とは、エンジンが1度に吸い込める混合気(空気と燃料が混ざった気体)の容積のことです。
エンジン内の容積が大きいほど燃やせるエネルギー量が上がり、総排気量も大きくなります。では、バイクの排気量について、もう少し詳しく見ていきましょう。
排気量が多いほどパワフルなエンジン
エンジンを動かすためには、混合気を燃やさなくてはいけません。混合気を急激に燃やす状態が「爆発」です。爆発によって発生する熱エネルギーの量は、「エンジンが1度に吸い込める混合気の容積」に比例します。
混合気(空気と燃料)が多いほど、大きなエネルギーを得ることが可能です。
つまり、バイクの総排気量が大きいほどパワフルなエンジンであるといえ、その分バイクのパワーも上がるため、取り回しや運転の技術が求められます。
エンジンのシリンダーとピストンの間が排気量に該当する
バイクの排気量とは、具体的にエンジンのどの部分が該当するのでしょうか。エンジンには、「シリンダー(気筒)」と、そのシリンダー内を上下に動く「ピストン」があります。そのシリンダーとシリンダー内のピストンの間の空間の大きさが、「排気量」に該当する部分です。
排気量は、一般的に「cc」や「cm³」の単位で示されるため、缶やペットボトルのドリンクなどをイメージすると、大きさをイメージしやすいでしょう。
排気量の計算方法は?
バイクの排気量は、ピストンが上下運動できる長さ「ストローク」と、ピストンの表面積から算出可能です。計算式としては、以下のようになります。
排気量=ピストン(ボア)の半径×ピストン(ボア)の半径×円周率×ストロークの長さ
上記は、1つの気筒の排気量を算出する計算式です。大きいエンジンを積んだバイクになると、4気筒エンジンなどもあるため、この場合は「排気量×4」でそのエンジンの総排気量を導き出せます。
総排気量別のメリット・デメリットとは?

総排気量によってバイクのエンジンパワーや車体サイズも異なるため、それにともなってメリット・デメリットも変わってきます。以下では、総排気量別のメリット・デメリットを表でまとめました。
| 総排気量 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ~50cc | ・燃費が良い ・車体価格が比較的安価 ・車体が軽く取り回しが楽 |
・30kmまでしか出せない ・二段階右折のルールがある ・車の流れに乗りづらい |
| 51~125cc | ・50cc未満の制限がなくなる ・維持費が原付と変わらない ・2人乗りが可能 |
・高速道路に乗れない ・2人乗り可でもパワー不足を感じる |
| 126~250cc | ・高速道路の走行が可能 ・車検がない ・バイクの車種が豊富 |
・高速道路を走行するにはパワー不足 ・車体が軽く風に煽られやすい |
| 251~400cc | ・高速道路や街乗りなどに使える ・十分なパワーを発揮できる |
・車検が必要になる ・維持費が大型バイクと変わらない |
| 401cc~ | ・高速道路の走行が可能 ・高性能なバイクが多い ・長距離走行にも向いている |
・車体が大きく取り回しが大変 ・購入費や維持費が高い |
前述のように、総排気量が大きいとバイクのエンジンパワーそのものが大きくなります。また、エンジンのサイズ自体も大きくなるため、必然的に車体が大きくなっていく傾向があります。これらを合わせて考えると、総排気量が大きいバイクは瞬間馬力が大きく、優れた加速性能と安定した走りができる点が大きな魅力です。
しかし車体が大きな分、取り回しがやや難しいといったデメリットが挙げられます。反対に、総排気量が小さくなると瞬間的なパワーは劣りますが、コンパクトで小回りが利き、停車時の安定感に優れます。
総排気量に応じて必要な運転免許や維持費が異なる
エンジンは、燃料と空気を吸い込み爆発を起こすことで、エネルギーを発生させて動力を得ます。つまり、排気量によってバイクのパワーが異なり、バイクを扱う難易度にも差が生じるため、排気量別に必要なバイクの免許が異なるというわけです。
また、バイクの排気量に応じて運転免許だけではなく、維持費にも差が生まれます。ここからは、排気量ごとに必要な運転免許や変動する維持費について確認していきましょう。
総排気量ごとに必要な運転免許
また、総排気量には大きく分けて5つの種類があり、総排気量ごとに異なる運転免許が必要とされます。その区分は、以下の表を参考にしてください。
| 総排気量 | 必要な運転免許 |
|---|---|
| ~50cc | 走行には16歳から取得できる原付免許が必要 |
| 51~125cc | 走行には16歳から取得できる小型限定普通二輪免許が必要 |
| 126~250cc | 走行には16歳から取得できる普通自動二輪免許が必要 |
| 251cc~400cc | 走行には16歳から取得できる普通自動二輪免許が必要 |
| 401cc~ | 走行には18歳から取得できる大型自動二輪免許が必要 |
総排気量によって変動する維持費
排気量が大きくなるとバイクのスペックが上がるため、車両そのものの値段や維持費が高くなるのが一般的です。
保険料においても、総排気量125cc以下のバイクまでは自賠責保険(共済)と合わせて「ファミリーバイク特約(任意保険)」に加入できます。しかし、126cc以上のバイクでは自賠責保険(共済)と合わせて各々のバイク保険に加入する必要があるため、維持費が高くなりがちです。
また、定期的にかかる税金においても、126cc以上ではバイク取得時と1年に1度の自動車重量税が必要ですが、125cc以下では1年に1度の軽自動車税のみと維持費に大きな違いがあります。
まとめ
バイクの排気量とは、エンジンが1度に吸い込める空気と燃料の容積のことです。排気量が大きくなるとエンジンパワーも大きくなり、それにともなって車体が大きくなる傾向にあります。排気量が大きいと取り回しが難しくなるだけでなく、必要な運転免許も異なるため注意が必要です。
また、欲しいバイクの総排気量によって、車両そのものの値段や維持費が高くなるケースもあるでしょう。そのような場合は、中古で状態が良いバイクを探せば車体料金を大幅に節約でき、その後必要となる維持費に備えることもできます。
バイク情報のポータルサイト『GooBike』では、全国の中古車も掲載しているため、総排気量によるメリット・デメリットを参考にお気に入りの1台を探してみてはいかがでしょうか。
本記事は、2023年4月7日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。