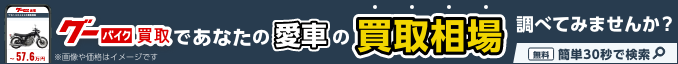�Х���2�������̥�ϤȤϡ����ˤʤ�ݻ���2���ܤ��������ʤɤ����
��������Х������Ѥ��Ƥ������Τʤ��ˤϡְ㤦������ΥХ�����⤦1����������פȹͤ������⾯�ʤ�����ޤ����̶��Ѥȥġ�����ѤǥХ�������ʬ�������פȸ�Ƥ���Ƥ������⤤��Ǥ��礦��
���ε����Ǥϡ�2���ܤΥХ����ʥ�����ɥХ����ˤ����������åȤȥǥ��åȤ�Ҳ𤷤ޤ���ʻ���ơ�������ɥХ�������Ĥ����ǵ��ˤʤ�Х����ΰݻ�����ݸ��ˤĤ��Ƥ���⤹��Τǡ����һ��ͤˤ��Ƥ���������
�Х���2������Υ��å�
�ޤ��ϡ��Х�����2�����������åȤ�3�ľҲ𤷤ޤ���
��Ū�˹�碌�ƻȤ�ʬ������
�Х����ϡ�����ˤ�ä����դʤ��Ȥ������դʤ��Ȥ�����ޤ���
�㤨�С��ᥬ���ݡ��ĥ����פϥϥ����ԡ��ɤ����Ԥ����դǡ��ġ���䥵�����åȡ�ƽ�����Ԥ�Ŭ���Ƥ���Τ���ħ�Ǥ��������ǡ����Τ��Ť��ۥ�����١�����Ĺ�����ᡢ��������μ�������ʥ�������¿�������������ؤȴ����䤹���ǥ��åȤ�����ޤ���
�ޤ�������1��Υ������������̳ؤ��̶С��㤤ʪ�ʤ�����Ū�ʥ�����Ǥΰ�ư���ʤȤ���ͥ��Ƥ��ޤ��������������ºǹ�®�١�30km��h�ˤν���2�;��ϤǤ��ʤ��ʤɤη�ޤ꤬���뤿�ᡢ�ġ���ˤ�Ŭ���Ƥ��ޤ���
����ΰ㤦�Х�����2����äƤ���С����줾������դ��̤�褫������Ū�˹�碌�ƻȤ�ʬ���뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
�ġ���ʤɤγڤ�������¿�Ͳ�����
�����פΰۤʤ�Х�����2����Ĥȡ���Ū�̤˻Ȥ�ʬ�����Ǥ�������ǤϤʤ������ԤǤ���ƻϩ������褬�����ƥХ����γڤ���������깭����ޤ���
�㤨�С��ġ������Ū�Ǥ���Х����ѡ����ݡ��ĥ����ס����ե����ɤ����Ԥ���ݤˤϥ��ե����ɥХ�������������Ǥ����⤷���ϡ��ӵ��̤ΰ㤦�Х�����������ꡢƱ���Х�����ǯ���㤤��������ꤹ��Τ�褤�Ǥ��礦��
���Х����ˤ�äơ����Ի��δ��Ф�������ηʿ��ϰۤʤ�ޤ����Х����ΰ㤤���̤��ơ�1������Ǥϵ��դ��ʤ��ä�������ȯ����������ʤɡ��Х������褬���ؽ��¤��ޤ���
������������Ǥ�Х����˾���
�Х�����������ƥʥʤɤ��¤�����硢1��Τߤξ���������������ƥʥ������ޤǾ��ޤ���
2������Ǥ���С��¤��Ƥ���֤������ΥХ����˾�뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ�����˾���Х�����긵�˳��ݤ��Ƥ����������ˤȤäƤϡ��礭�ʥ��åȤȤ�����Ǥ��礦��
�Х���2������Υǥ��å�
�Х���2������ˤ�¿���Υ��åȤ���������ǡ��ʲ��Τ褦�ʥǥ��åȤ⤢��ޤ���
�����ݴɾ�꤬ɬ�פˤʤ�
�Х�����2���ݴɤ���ˤϡ�����ʤ�˹������ڡ����γ��ݤ�ɬ�פǤ��������������˹�����־�䥬�졼��������С�����ʤ��ݴɤǤ��뤫�⤷��ޤ������������Է������ߤʤɤ˽���Ǥ����硢��������־��ڤ�뤫���Х�����2���ݴɤǤ���ʪ���õ��ɬ�פ�����Ǥ��礦��
����Ǥ�����ˤ�äƤϡ��ݴɾ�����ݤ��뤿�����־���������ʤɤηк�Ū����ô���礭���ʤäƤ��ޤ������줬����ޤ���
�ݻ���2��ʬ�ˤʤ�
�Х�����������2��ˤʤ�С��ݸ���������ʤ����ݤ����ѡ���������塢�ָ���ʤɤΰݻ����2��ʬ������ޤ����ޤ�����������ֺѴ��֤�2��ʬ�ŤʤäƤ��ޤ���������ͤ�����Ǥ��礦��
�����ΰݻ��������������˲ä��ơ�����������������ݤλ��֤�2�ܤˤʤ뤿�ᡢ����ޤǰʾ�˥��ƥʥ˻��֤����������ˤ�α�դ���ɬ�פ�����ޤ���
�����ʤۤ�������äƤ��ޤ�
�Х�����2���ͭ���Ƥ���ȡ��Ĥ������ʤۤ��ΥХ�������䤹���ۤ��ΥХ����ˤФ����äƤ��ޤ����⤷��ޤ����㤨�С��緿�Х������淿�Х�����2������ξ�硢�����̤��ڤ����ڤ˾����淿�Х����˾�����٤��������ǽ��������ޤ���
�����ˤ������ʤ��ʤ�С��ݻ�����Ƕ⤬̵�̤ˤ����äƤ��ޤ���2��������̣���ʤ��ʤäƤ��ޤ��Ǥ��礦��
�ݸ��ʤɥХ���2������Ǥ�����ݻ���

��������ϡ��Х�����2���ͭ�������ˤ�����ݻ���ˤĤ��ơ��Ƕ���ݸ��ʤɤι����̤˾ܤ������⤷�ޤ���
�Ƕ�
�Х����ˤ�����Τϡַڼ�ư���ǡפȡּ�ư�ֽ����ǡפǤ����dzۤ��ӵ��̤ˤ�ä���ư���ޤ����㤨�С��ӵ���90�հʲ��θ��դ�2,000�ߡ�125ccĶ���250cc�ʲ��ΥХ�����3,600�ߡ�250��Ķ��6,000�ߤηڼ�ư���Ǥ�������ޤ���
��ư�ֽ����Ǥϡ�125�հʲ��ΥХ������оݳ��Ȥʤ뤿��0�ߤǤ���125ccĶ���250�դΥХ����ϡ�������Ͽ�κݤ˽�ͭ�Ԥ��Ф���4,900�ߤ�ȯ�����ޤ���250��Ķ�ΥХ����ϡ�������Ͽ����3ǯʬ��5,700�ߡ����θ�ϼָ��κݤ�2ǯʬ��3,800�ߤ�Ǽ�դ��ޤ���
�Х�����2����ľ��ϡ��������Ƕ⤬2��ʬ����������α�դ���ɬ�פ�����Ǥ��礦��
���͡�
��̳�ʡ�����������
�ڼ�ư����
���ڸ��̾ʡÿ��ֿ�����Ͽ���ˤ����뼫ư�ֽ����Ǥ��dz�
�Х����ݸ�
�Х����˾��ݤ�ɬ�פ��ݸ��ϡּ������ݸ��פȡ�Ǥ���ݸ��פ�2����Ǥ����������ݸ����ݸ����ϡ����츩��Υ��ʤɤΰ����ϰ������ơ��ӵ��̤������֤ˤ�ä���ư���ޤ���
�㤨�С�125�հʲ��ξ��Ϸ�����֤ˤ�ä�ǯ��2,662���6,910�ߡ�125�Տ��250�հʲ��ξ���ǯ��2,840���7,100�ߤǤ���
Ǥ���ݸ����ݸ����ϡ����Ƥ����ݸ���Ҥ�������ơ������̵ͭ�ˤ�ä���ư���ޤ���
�����ɥ����ӥ�
�Х����������桢�ѥ䥭���Ĥ����ߤʤɤΥȥ�֥�ǿ�ư�������ʤ��ʤäƤ��ޤ���ǽ���⥼���ǤϤ���ޤ����κݤϡ������ɥ����ӥ���Ƥ���б����Ƥ�餦ɬ�פ�����Ǥ��礦��
�㤨�С�JAF�Υ����ɥ����ӥ������Ѥ���ݡ�����ˤʤ����1ǯ����������+ǯ�����5,500�ߤ��ʧ��ɬ�פ�����ޤ��������ӥ����оݤϡֲ������ܿ͡פʤΤǡ��Х���������ˤ�����餺�����Ʊ�ۤǤ���
�ʤ���JAF�β����̵���ǥ����ɥ����ӥ���������ޤ����������ξ��ϥȥ�֥�����Ƥˤ�ä�1��3,330�ߏ��1��6,770�ߤ�������ޤ���
���͡�
JAF��������åȡ����ѤˤĤ���
���ƥʥ�����
���ƥʥ����ѤȤ��Ƥϡ����������2ǯ�˰��٤μָ����������ޤ������������ӵ��̤�250�հʲ��Ǥ���мָ���������̳�Ϥʤ����ᡢ�ָ����Ѥ�0�ߤǤ���
250�դ�Ķ����Х����μָ����Ѥϡ������ȼԤ˰��ꤹ��ָ��ȥ桼�����ָ��Τɤ����Ԥʤ����ˤ�ä���ư���ޤ����㤨�С�400�դΥХ����ξ�硢ˡ�����ѡ�������������ѡ��ѡ��Ĥθ���ʤɤ��碌��5�������٤����Ǥ���
������
�Х����ξ����ʤϡ����Ū�ʸ�ɬ�פʥ������ե��륿������������ʡ��䥯�����ȡ������䡢�֥졼���ѥåɤ�ǥ��������������ʤɤ��ޤ��ޤǤ���
�ּ�ˤ�äƾ����������ư���뤿��쳵�ˤϤ����ޤ���ʿ�Ѥ���3�������٤�����Ȥ���Ƥ��ޤ���
������ɥХ�����������
�����Ǥϡ�������ɥХ��������ֺݤ˽Ż뤷����2�ĤΥݥ���Ȥ���⤷�ޤ���
1���ܤ����Ӥΰ㤦�Х���������
������ɥХ��������ֺݤϡ�1���ܤȤϥ���������Ӥ��ۤʤ��Τˤ���Ȥ褤�Ǥ��礦��
�㤨�С��֥ġ�����ѡפȡֳ�����ѡפΥХ������ͭ����С���Ū�˹�碌�ƻȤ�ʬ�����ޤ����ޤ����ӵ��̤ΰ㤦�Х��������֤Τ⤪������Ǥ���
����������Ӥ��ۤʤ�Х��������֤��Ȥǡ��ɤ��餫�������Фäƾ�äƤ��ޤ��ǥ��åȤ����Ǥ���Ǥ��礦��
�ݸ��Υե��ߥ�Х�����������Ѥ���ʤ�125�հʲ�
��Ǥ���ݸ����ݸ�����ʤ�٤��¤��ޤ������פȤ������ϡ��ݸ��Υե��ߥ�Х���������оݤȤʤ�125�հʲ��ΥХ��������֤Τ���������Ǥ���
�ե��ߥ�Х�������ϡ���ư�֤�Х�����Ǥ���ݸ��˥��ץ����Ȥ����դ������Τǡָ�������פȤ�ƤФ�ޤ����̾�ΥХ����ݸ��������ʥ֥�����ѤǤ��������礭����ħ�Ǥ���
����Ū�ʥե��ߥ�Х�������Ǥϡ�����оݤΥХ�����������¤��ʤ����Ȥ�¿�����ᡢ2��ʾ�Х������ͭ����ݤ�Ŭ�����ݸ��Ȥ�����Ǥ��礦��
�Х���2������Τ���������Ȥ߹�碌
�Ǹ�ˡ��Х���2�������Ƥ���Ƥ������ˤ�������ΥХ������Ȥ߹�碌��Ҳ𤷤ޤ���
��������ɥХ�����125�հʲ��γ������
��������ɥХ�����125cc�ʲ��γ�����ѥХ������Ȥ߹�碌�ϡ��Х�������̣���緿�ΥХ����˾�뤱��ɡ����Υ��ư�ˤϤ��ޤ�Ȥ������ʤ�����Ŭ���Ƥ��ޤ���
�ޤ���125�հʲ��ΥХ�����Ǥ���ݸ��Υե��ߥ�Х���������оݤȤʤ뤿�ᡢ�ݻ�����ޤ��������ˤ⤪������Ǥ���
�㤨�С��ۥ���ΥХ����Ǥ��������硢400X�ȥ�������Ȥ߹�碌�ʤɤ����ޤ���������������������ˡ������ʼּ���Ȥ߹�碌�Ƥ�褤�Ǥ��礦��
��������ɥХ����ߥ��ե����ɥХ���
��������ɥХ����ߥ��ե����ɥХ������Ȥ߹�碌�⤪������Ǥ���Ʊ���ӵ��̤Ǥ��äƤ⡢��������ɥХ����ȥ��ե����ɥХ����ǤϾ�꿴�Ϥ�Ŭ����ƻϩ���ۤʤ�ޤ���
���Τ��ᡢ��®ƻϩ�Υġ������ƻ�Ǥ����Ԥʤɡ��Х����Ǥ���������ƻϩ�����äƳڤ��ߤ������˺�Ŭ�Ǥ���
�Ȥ߹�碌����Ȥ��Ƥϡ���������GSX-R1000R��V-���ȥ�����250SX�ʤɤ����ޤ���
�緿��������ɥХ����ߥߥ˥Х���
�緿��������ɥХ����ߥߥ˥Х����⡢2��������Ȥ߹�碌�Ȥ��ƿ͵��Ǥ�����������ɥХ�����125�հʲ��γ�����Ѥ��Ȥ߹�碌��Ʊ�ͤˡ��緿��������ɥХ����Ǥϥѥ�����ꤹ���뤿����Υ�������Ȥ�������Ŭ���Ƥ��ޤ���
�㤨�С��ۥ����CB1300SF�ȥ���ХϤ��Ȥ߹�碌�Ǥ���С�����ХϤ�50�հʲ�����ô�ηڤ������ӵ��̼֤ʤΤǰ����䤹����������Ǥ������ҤΥ�����Ʊ�͡��ե��ߥ�Х�����������ѤǤ���Ǥ��礦��
�ޤȤ�
�Х�����2������ˤϡ����Ӥˤ�äƻȤ�ʬ�����Ǥ��롢1�椬������Ǥ�Х����˾���ʤɤΥ��åȤ�����ޤ��������ǡ������ݴɾ�꤬ɬ�פˤʤä��ꡢ�ݻ�����������ȡ��ǥ��åȤ⤤���Ĥ����뤿�����դ�ɬ�פǤ���
������ɥХ����ϡ�1���ܤȤ����Ӥ䥸���뤬�ۤʤ��Τ����֤ȡ��ɤ��餫�����Ф���˾�äƤ��ޤ����֤�����Ǥ��礦���ޤ���125�հʲ��ΥХ��������֤ȡ��ե��ߥ�Х����������ѤǤ����ݻ�����ޤ������ǽ��������ޤ���2������Υ��åȤȥǥ��åȤ��İ����������Ǻ�Ŭ���Ȥ߹�碌��Ƥ�����Х����饤�դ���ڤ���Ǥ���������
�ܵ����ϡ�2023ǯ1��5�������ξ���Ǥ����������Ƥμ»ܤϡ������Ȥ���Ǥ�Τ�Ȱ�������ͭ�������θ���Ƥ����Ѥ��������褦���ꤤ�פ��ޤ���
�ǿ���������
-
�Х������Τ� 2025.05.22 up �Х����ηڼ�ư���ǡʼ��̳�ˤȼ�ư�ֽ����ǤϤ����顩�ӵ��̤��Ȥ��dzۤ��ʧ����ˡ�ˤĤ��Ʋ���
-
�Х������Τ� 2025.05.22 up �Х����μ������ݸ������ʤȤϡ��ּ�ˤ�������ˡ�ΰ㤤
-
�Х������Τ� 2025.05.22 up �Х�����Ǥ���ݸ��ʥХ����ݸ��ˤ�̵�̡�������Ƥ���Ȥߡ��������Υݥ���Ȥ����
-
�Х������Τ� 2025.05.22 up �Х����μ������ݸ��β�����������ˡ�Ҳ�
-
�Х�����ݻ����� 2025.05.14 up �Х����Υ����䥵�����δ����μ��ȸ���������̥���������Ŭ��ɽ������å�
- ��äȸ���