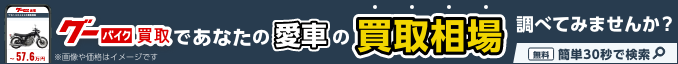バイク用ETC装置の種類や取り付け方法
ETCは高速道路でのバイク走行時に専用レーンを通過出来るので、料金支払いの手間も省けて便利です。特にグローブを装着しているライダーにとっては必須だと言えるのではないでしょうか。今回はETCに関する基本的知識を紹介します。
そもそもETCとは
ETCとは「Electronic Toll Collection System」の略です。有料高速道路の利用料金を、車両に搭載した端末(車載器)と料金所のゲートに設置されたアンテナとの通信で処理するシステムです。料金所で停止する必要がなく、しかもキャッシュレス決済なので、特にバイクにとってはメリットが大きいです。ゲートを通過する時間が大幅に短縮されることで、渋滞の緩和に繋がっています。
通行料金が割引される「ETC割引」の他、深夜や休日等の割引を受けることが出来ます。高速道路会社によって違いはありますが、高速料金が3割引になるケースもあります。サービスエリア/パーキングエリアに直結した「スマートIC」は、ETC搭載車両だけが利用可能です。バイクのツーリングでは集合・休憩・解散場所にサービスエリアを利用するケースがあるので、スマートICから乗り降り出来れば利便性は格段にアップします。
必要機器の取り付け方法とコスト
ETCで快適な高速道路走行を楽しむには、車載端末が必要です。大きく分けると本体とアンテナが一緒になっている「一体型」と、両者が分かれている「分離型」があります。一体型のメリットは端末価格と取り付け費用が安いことです。分離型はETCの料金決済に必要なクレジットカードを収納する本体部分を、目立たない場所に設置出来るので、盗難や故障のリスクが低減されるのが利点です。
バイクのETC普及率は車よりも低いのですが、その理由の一つにバイク用車載器のコストの高さがあげられます。ETCのシステムはバイクと車とで違いはありませんが、バイク用車載器はバイクの特性上、防水性・耐震性を高める必要があるため、車よりもコストが高くなっています。
ただ現在では、バイクのETC利用を促進するためにバイク用ETC取り付け助成金の支給等のキャンペーンがよく行われています。ETCや高速道路のウェブサイト等で告知されているので、こうした機会を上手に利用してETCを取り付けましょう。

取り付けの手間とコスト
ETC端末を購入・取り付け、決済用のETCカードを入手しても、それだけでETCが利用出来るわけではありません。ETCの端末情報を登録し、利用可能な状態にする「セットアップ」というプロセスが必要で、これはディーラーや用品店に依頼します。本体+取り付け工賃+セットアップ料金という3つのコストが掛かるわけです。端末は自分で取り付けることも可能ですが、購入時にセットで依頼する方がリスクも少なくておすすめです。
これからETCを取り付けるなら「ETC2.0」対応端末がおすすめ
次世代型のETCサービスとして運用が始まったのが「ETC2.0」です。高速道路利用料金の収受に加えて、広範囲の渋滞や交通規制に関する情報、前方で起こっている渋滞情報を知らせる安全運転支援といったサービスを提供してくれるものです。道路沿いに設置されたITSスポット(通信アンテナ)とETC2.0対応車載器(これまでDSRC通信という名前で呼ばれていたもの)を、高速かつ大容量の通信で接続することで可能になった新情報サービスです。
料金面のサービスはまだ限定的で、首都圏なら圏央道(新湘南バイパスを含む)の割引料金が適用されている程度です。現状は従来型のETCでも特に不都合はありませんが、将来的にはETC2.0への置き換えが進んでいく方向です。さらに同一の出口ならどのルートを通っても料金が変わらないという新しい料金体系が、ETC2.0にのみ提供される計画です。従来型と比較すれば端末料金がやや高いのですが、これからETCを導入するライダーならETC 2.0の方が安心と言えそうです。
おすすめのETC装置を紹介
ETCを選ぶ際に重要なポイントは以下の4点です。
サイズが大きかったり重かったりすると、運転時の操作性に影響します。また、バイクは雨風にさらされるため、防水性や防塵性は高性能でなければいけません。上記を考慮した場合の、おすすめのバイク用ETCをご紹介していきましょう。
MITSUBA MSC-BE700W
バイクの見た目を壊したくないというライダー目線で開発されたETC車載器。そのため、ETCの作動状態を示すインジケーターが、非常にスリムなのが特徴です。ミラーなどの陰に取り付けられるので、見た目には影響を与えません。アンテナ部分もコンパクト設計なうえに、取り付け角度の自由度が高いです。また、雨風にさらされやすいアンテナやインジケーターは、最高ランクのIP68とIP66を達成しているので、バイクでも安心して使用することができるでしょう。
MSC-BE700Wスペック
MITSUBA MSC-BE21
ミツバサンコーワの一体型バイク用ETCです。分離型と違い、本体や重量が大きくなりますが、配線が極力ないため取り付けが簡単で、価格が安いのがメリットとなります。MSC-BE700Wと違い、ETC2.0には対応していませんが、ETCを簡単に取り付けたいライダーにおすすめのモデルです。
MSC-BE21スペック
日本無線 JRM-21
ETC2.0に対応し、IP67とIP66の防水防塵性能がある高性能モデルです。上蓋を閉めた状態なら、水に沈めても大丈夫なIPX7の防水性能を持つため、洗車や嵐などの環境でも安心でしょう。また、バイク専用耐震設計で20Gまで耐えることができます。
RM-21スペック
日本無線 JRM-12
日本無線の一体型バイク用ETCです。ETCカードの読み取り方法は挟み込み式を採用しており、カバーのロック部分が大きく開閉しやすい設計になっています。取り付けも電源ケーブルだけなので、ETCの導入が簡単に行えるモデルです。
JRM-12スペック
ミツバサンコーワや日本無線の製品には、ETC2.0に対応していない、値段の安い分離型ETCもあります。しかし、導入後長く使うことを考えれば、価格は高くなりますがETC2.0に対応したモデルを選ぶことをおすすめです。
まとめ
ETCはバイクにとって、車以上にメリットが多いシステムだと言えるのではないでしょうか。便利なETCを装着して、高速道路のライディングをより快適に楽しみましょう。
本記事は、2016年7月14日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
最新記事一覧
-
バイクを維持する 2025.11.17 up バイクのバッテリー回収はどこでする?無料・費用・注意点まで徹底解説
-
バイクを維持する 2025.11.17 up バイクのETCは移設できる?費用・再セットアップ方法・注意点まとめ
-
バイクを維持する 2025.11.17 up フロントフォークのサビ対策完全ガイド|原因・落とし方・修理費用・予防法まで紹介
-
バイクを維持する 2025.10.06 up バイクを長期保管する方法!数年~10年保管時の注意点と再始動時のチェック項目も紹介
-
バイクを維持する 2025.10.06 up バイクの車検は何ヵ月前から?前倒しのメリットや費用などバイク車検の基本を解説
- もっと見る