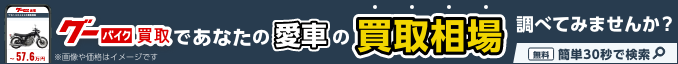熱狂的ファンを獲得するハーレー(ハーレーダビッドソン)、その魅力や人気の秘密とは?
ハーレーダビッドソンと言われれば、バイク乗りでなくても、大型で洗練されたバイクをイメージ出来るのではないでしょうか。ハーレーにはバイク好きを熱狂させる確かな魅力とインパクトがあります。
ここでは、ハーレーの「何」が魅力なのか、その謎を解明していきましょう。
ハーレーダビッドソンの歴史
現在、様々なメディアでハーレーが取り上げられますが、ハーレーと言えば「若者の夢」「男の夢」「バイク乗りの夢」等、多くの方を魅了する憧れの存在です。
ハーレーダビッドソンは、1903年、『シリアルナンバー1』と名付けられたエンジン搭載型自転車が好調な売上を博したことで、現在の大手バイクメーカー、『ハーレーダビッドソン』へと成長を遂げました。
シリアルナンバー1は、ハーレーの創始者であるウィリアム・S・ハーレー氏とダビッドソン兄弟(弟:アーサー・ダビッドソン、兄:ウォルター・ダビッドソン氏)の共同開発による傑作で、この自転車の売上があったことでエンジン開発やバイク開発が可能になったと言われています。
実際に会社として創設されたのは後の1907年で、ここからは株式上場を経て本格的なバイクメーカーとして会社を拡大し、同年には『モデル3』と呼ばれるエンジン搭載型バイクを150台製造した実績があります。
日本での展開
日本に始めてやってきたハーレーとしては、『サイレントグレーフェロー(意味:静かな灰色の友達)』と呼ばれる、エンジン搭載型自転車と同等のスペックを持つ『モデルE』ですが、この当時多くの日本人を魅了したのがハーレーの『Vツインエンジン(V2型)』です。
Vツインエンジンは他のバイクメーカーでも開発され、今ではすっかりお馴染みの形状ですが、この画期的なフォルムとスペックを有したエンジンの創始者は、紛れもなくハーレーダビッドソンだと言われています。
1900年代中期にかけては、車体・エンジンともにさらなる改良が重ねられ、私たちがよく知るハーレーダビッドソンの原型が既に存在しています。その頃から21世紀にかけて登場し始めたバイクには、
等が挙げられます。
ハーレーの魅力や他のブランドとの違い
いつの時代もハーレーのバイクに熱狂的なファンが絶えないのは、最先端の技術と大迫力のマシン性能で見る人・乗る人を飽きさせない進化が続いているからではないでしょうか。
ライダーがバイクに求めるものは人それぞれですが、ハーレーのバイクは方向性が異なるニーズを自然と満たしてくれるようなスペックを兼ね備えています。
中でも、ハーレーの魅力としてよく挙げられるのが、創設以来改良が重ねられてきたエンジンです。実際にハーレーの鼓動を間近で体感すると、他の大型バイクでは感じられないような躍動感や迫力を目の当たりに出来ます。また、エンジン音は低くドッシリと響くサウンドで、アメリカン好きを虜にしてしまうほどの魅力があります。
かつて、海の向こうで開発されたサイレントグレーフェローは、その名前から、ハーレー氏やダビッドソン兄弟がバイクに対して特別な愛情を持っていたことがよく分かります。長い年月が経った今でも、そんなハーレーのバイクはライダーに寄り添う相棒として多くのライダーを魅了し、この先もそうあり続けるのではないでしょうか。

マシンの性能やスペック
ハーレーのマシン性能やスペックは、車種によっても異なりますが、代表的なエンジン性能と類するファミリー(シリーズ)を大まかに把握出来ると、マシン性能をイメージしやすくなります。そこで、ハーレーの歴代エンジンと、類するファミリーを以下にまとめました。
車種情報(排気量やカラーリングなど)
「ハーレーと言えば大型バイク」のイメージ通り、車種は全て400cc以上の大型クラスのみでラインナップされています。下は750ccから上は1801ccとその幅は広く、2017年モデルにもファミリーごとに多くのラインナップがあります。
また、カラーリングは黒やシルバーなどの洗練されたものから、レッドやブルーのカジュアルなものまで様々です。
新車や中古車の価格帯
ハーレーの値段は排気量やファミリーによっても異なりますが、新車で数百万円、中古車でも数十万〜数百万円等が一般的な価格帯です。中古車でも状態がよく人気が高いものほど高額になりますが、新車購入と比べれば「頑張って貯金しよう」 と思える価格で販売されている場合もあります。
ハーレーへの憧れを形にするためにも、この機会に気になる種類や中古車市場の価格帯をチェックしてみましょう。
まとめ
ハーレーの魅力に惹かれた方は、ファミリー別の種類やスペックを確認して、お気に入りの一台を探してみてはいかがでしょうか?多くのライダーを魅了するハーレーのマシンで、心地良いエンジン音や振動、乗り心地を体験してみてください。
本記事は、2017年11月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。