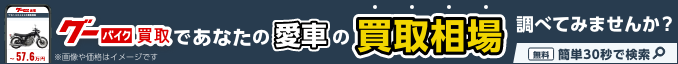コンパクトだけど馬力十分!原付二種・小型バイクとは?
外に出れば誰しも一度は目にしたことがある原付バイクですが、実は一種・二種と区別があります。今回は原付二種について解説します。
原付一種・原付二種の違い
日本では排気量が50cc未満の原付バイクを原付一種(第一種原動機付自転車)と呼び、50cc以上125cc以下の原付バイクを原付二種(第二種原動機付自転車・小型自動二輪車)と呼び、区別しています。それぞれ排気量が異なることから必要な免許も異なり、原付一種では原付免許(もしくは普通自動車免許)、原付二種では小型限定普通二輪免許が必要です。どちらも車体のサイズにそれほど大きな差が無いため、瞬時に原付区分を把握するのは難しいようにも思えますが、原付一種と原付二種ではナンバープレートの仕様が異なります。そのため、道路上ではナンバープレートを見て原付区分を確認するのが一般的です。
原付二種の特徴
小型二輪や小型バイク等の愛称で親しまれる原付二種の多くは、一般的な原付バイクのサイズやデザインを踏襲しつつ、走行性能や自由度を高めたバイクと言えます。一般道路で原付区分を確認するには、前項で触れたナンバープレートを確認します。黄色ナンバーやピンクナンバーと呼ばれる色付きナンバープレートが装着されていれば、それらのバイクは原付二種に当たります。具体的には、排気量50cc以上90cc未満のバイクには黄色ナンバーが付けられ、90cc以上125cc以下のバイクにはピンクナンバーが付けられています。
原付二種だから出来ること

見た目に大きな違いが無くても、原付一種・二種では走行時の条件が大きく異なります。たとえば、原付一種が法定速度30km/hと定められているのに対し、原付二種は60km/hでの走行が許可されています。また、二人乗り走行が禁止されているのは原付一種のみで、原付二種では一般道路での二人乗り走行が許可されています。高速道路や自動車専用道路の走行は出来ませんが、自動車に劣らない速度で一般道路を走行出来る点は、通勤通学を始めとした多くの場面で活躍するのではないでしょうか。
原付二種の免許取得の流れや費用、必要書類
125cc以下のバイクを走行するには、最低限2種類の免許が必要になります。
上記の免許は、以下の条件を満たさなければ取得できません。
取得方法には以下の2種類があります。
教習を受ける
公安委員会が指定している教習所で免許を取得する方法が一般的でしょう。教習所での免許交付までの流れは以下の通りです。
教習所への登録から免許交付までの流れ
ポイント
運転免許センターでかかる費用(2018年11月時点)
免許の申請手続きに必要な物
ダイレクト受験(一発受験)
教習所にいかず、各都道府県の運転免許センターで受ける方法です。教習所は数週間〜数カ月通わなければいけませんが、必要な技能や知識が身についていれば1日で免許を取得することが可能です。
免許取得までの流れ
ダイレクト受験の場合、教習所で受ける技能試験や適性試験、応急救護講習をそこで受ける必要があります。持ち物は基本的に一緒ですが、料金はダイレクト受験の方が高くなります。
免許申請手続きに必要な費用
合計で22,550円かかりますが、教習所に通うと十数万円の費用が必要なので、技能と知識が身についている人はダイレクト受験を受けてみるのも良いでしょう。
おすすめの原付二種のバイク3選
原付二種のバイクは、種類が多くないですが、長い間人気のあるモデルが販売されています。その中でもおすすめできるモデルを3つご紹介しましょう。
HONDA スーパーカブ110
業務用としても多くの採用実績があるスーパーカブは、小売価格が30万円を切るという低価格と62.0km / Lの低燃費が魅力で、2018年に販売60周年を迎えました。
HONDA PCX ハイブリッド
ガソリン車もあるPCXですが、リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載したハイブリッドモデルの製品があります。軽量化にもこだわっており、スポーティな見た目も特徴の一つです。
YAMAHA シグナスX SR
スクータータイプのバイクで、シート下の収納は約29Lとゆとりのある容量のバイクです。50ccのスクーターを使っていたライダーには、乗りこなしやすいモデルでしょう。
まとめ
原付一種のコンパクトな車体をそのままに、自由度が高まった原付二種であれば、より快適なバイクライフが送れるのではないでしょうか。二人乗り走行が出来るので、ちょっとしたツーリングや遠出にもおすすめです。速度と馬力を重視した原付選びなら、原付二種を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本記事は、2016年4月25日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。