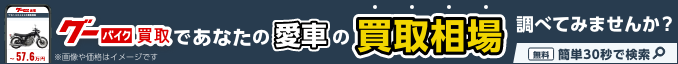�ӽХ��������Ǹ��եХ����˾��ʤ��ʤ롩�ӥ������������Ƥ�125cc�Х�����̥�Ϥ�Ҳ�
2022ǯ11��˻ܹԤ��줿��ʿ��32ǯ������2ǯ���ӽХ��������פϡ������ǺǤ⸷�����ӽХ��������Ȥ�����衼���åѤΡ�EURO5�פ�Ʊ���Ȥ����Ƥ��ޤ���
50�եХ����ˤĤ��Ƥ�3ǯ��ͱͽ��Ϳ�����ޤ����������δ��¤Ǥ���2025ǯ11���Ť��Ƥ��ޤ���
�������ܵ����Ǥϡ��ӽХ��������γ��פȵ��������եХ�����Ϳ����ƶ���125cc�Х�����̥�ϤʤɤˤĤ��Ʋ��⤷�ޤ���
���⤽���ӽХ��������Ȥϡ�
2022ǯ11����ڸ��̾ʤϥХ����ˤĤ��Ƥο������ӽХ���������ܹԤ��ޤ���������ˤ���2025ǯ11��鸶�եХ����˾��ʤ��ʤ�ΤǤϤʤ����פ��¤ˤʤäƤ������⤤�뤫�⤷��ޤ���
�Х����ȳ����괬���Ķ����礭�ʱƶ���ܤ��Ƥ����ӽХ��������Ȥϡ����⤽��ɤΤ褦�ʤ�ΤʤΤǤ��礦����
�ӽХ��������Ȥϡ�
�ӽХ��������Ȥϡ����ڸ��̾ʤ�����ƻϩ������ξˡ�ˤ�äƵ��ꤵ��롢�ӵ�����ǻ�٤�������ܺ��Τ��Ȥ�ؤ��ޤ���
¬�ꤵ����ӵ������ϰ����ú�ǡ�CO�ˡ�ú�����ǡ�HC�ˡ����ǻ���ʪ��NOx�ˤ�3����ǡ��ָ��κݤ�¬�ꤵ����ӵ��������ݰ´��ο����⤫�ɤ�������ǧ����ޤ���
�ӽХ�����������Ū�����
���ܤ��ӥ�����������ˤϡ�1966ǯ����Ƴ�����줿�������֡ʼ�ư�֡ˤ��Ф�������ú�ǡ�CO�ˤε�������ϤޤäƤ��ޤ���
��������ꥫ���Ի����Ǥϡ��ӵ������ˤ�륹��å�������ˤʤäƤ��ޤ����������ơ����Τ˰��ƶ���ܤ�ͭ��ʪ���κ︺����Ū�Ȥ��ơ������ú�ǡ�CO�ˤ�ú�����ǡ�HC�ˤε������ߤ����ޤ�����
������������Ū�ʴĶ�����ؤΰռ��ι�ޤ�⤢�ꡢ���ܤǤ��ӵ������������Ϥޤä��ΤǤ������θ塢1973ǯ�ˤ�ú�����ǡ�HC�ˤ����ǻ���ʪ��NOx�ˤε������Ԥʤ���褦�ˤʤꡢ�����1978ǯ�ˤ������ǺǤ⸷�����Ȥ���줿�ӵ������������ܹԤ���ޤ�����
���ߤϡ��ϵ岹�Ȳ��θ����Ȥʤ벹�����̥����κ︺����Ū�ȤʤäƤ��ޤ������ӵ������������ʳ�Ū�˸������ʤäƤ��ޤ���
���Τ褦��ή�줬���ꡢ�����ǺǤ⸷�����Ȥ����Ƥ��벤���Ρ�EURO5�פ�Ʊ���Ǥ��������2ǯ�ӽХ��������פ��ܹԤ��줿�ΤǤ���
�ӽХ��������Ǹ��եХ����˾��ʤ��ʤ롩
�ӽХ����������ܹԤ��줿���Ȥǡ��ºݤˤɤΤ褦�ʱƶ�������ΤǤ��礦����
����2ǯ�ӥ��������Ϸ�³�����֤ˤ�Ŭ��
2020ǯ12����ӥ����������оݤȤʤä��Τϡ����ӵ��̤ο����֤ΤߤǤ�������������2022ǯ11���Ϸ�³�����֤��оݤȤʤꡢ����2ǯ�ӥ��������ꥢ���Ƥ��ʤ���ξ������Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ�����
�����������հ��ˤĤ��Ƥϡ�2025ǯ10�����ޤ��ӥ����������оݤȤʤ�Τ�ͱͽ����Ƥ��ޤ���
�ֺּܼ��ξ�������֡�OBD���ˤ���ܵ�̳��
����2ǯ�ӥ��������ˤ�����ؼ֤��Ф��ơ��ӽХ���������������֤�������ƻ뤹������̤����ֺּܼ��ξ�������֡�OBD���ˡפ���ܤ���̳�դ����ޤ�����
OBD���Ȥϡ���ξ����ܤ��줿����ԥ塼�����ˤ�뼫�ʸξ���ǥ����ƥ�Τ��Ȥǡ���ξ�ξ���Ǿ���Τۤ���®�١������ž���ʤɤξ��������Ǥ��ޤ���
�ޤ�������ԥ塼�������۾���Τ����ݤϡ������å�����������ٹˤ��ɥ饤�С����Τ餻�뵡ǽ������ޤ���
����2ǯ�ӥ��������Ǥ����ӵ��̤�50cc�ʲ������ĺǹ�®�٤�50km��h�ʲ��θ�ư���ռ�ž�֤�������ؼ֤ˡ�OBD����Ƴ������̳������ޤ�����
50cc�ʲ��θ��եХ����ˤĤ��Ƥ�2025ǯ10�����ޤǤȤ���ͱͽ���֤��ߤ����Ƥ����ΤΡ�OBD������ܤ���ȼ��β��ʤ���ۤˤʤäƤ��ޤ����Ȥ���������Ƥ��ޤ���
���Ǥ˹����Ѥߤθ��եХ����Ͼ���
�Х������괬���Ķ���ˡΧ���Ѳ����Ƥ����ʤ��ǡ��ָ����äƤ��븶�եХ����ϡ����Τޤ�äƤ��Ƥ�����פʤΤ����������פ��¤˻פäƤ������⾯�ʤ��ʤ��Ǥ��礦��
�������������餤���ȡ�������Ͽ����˸��եХ������������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ʤ��ΤΡ����Ǥ˾���Ԥ������Ѥߤ�����θ��եХ����ϡ�����³����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����������äƸ����Ǥϡ��Ǥä��㤤�ؤ���Ƥ����ɬ�פϤʤ��Ǥ��礦��
125cc����θ��եХ������������롩125cc�Х�����̥��

2023ǯ9��ٻ�ģ�ϡ����աʸ�ư���ռ�ž�֡��ȵ��Ǿ�֤Ǥ����ӵ��̤�����50cc�ʲ�����125cc�ʲ��˸�ľ����Ƥ��ʤ���ȯɽ���ޤ������оݤȤʤ�Τ��ӵ���125cc�ʲ��ǡ��ǹ���Ϥ�4kW��5.4ps�ˤޤǤΥХ����Ǥ���
�Ĥޤꡢ125cc�ΥХ��������ޤǤ�50cc�θ��դ�Ʊ����ʬ�ˤʤ뤫�⤷��ʤ��ΤǤ���
�����ǡ������Ǥϸ������ܤ�Ƥ���125cc�Х�����̥�Ϥ�Ҳ𤷤ޤ���
�ݻ��¤�
250cc����Ӥ���125cc�ϼ��β��ʤ��¤����ӵ��̤�����������dz���ɤ��Τ�̥�ϤǤ����Ƕ�ʷڼ�ư���ǡˤ��ݸ����ʼ������ݸ���Ǥ���ݸ��ˡ�������ʤɤξ����ʤ����Ū��250cc���¤��ޤ����ޤ���
�ޤ����ݸ���Ҥˤ�äƤ�ۤʤ�ޤ�����Ǥ���ݸ��Ǥϥե��ߥ�Х��������Ȥ��뤿�ᡢñ�Ȥ�Ǥ���ݸ��˲�������������Ѥ��ޤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
�ڤ��ư����䤹��
125cc��250cc��400cc����Ӥ��ơ����Τ����������̤ʥ�ǥ뤬¿�����ᡢ�����Ǥⰷ���䤹���Ȥ������åȤ�����ޤ���
�ޤ������̤Ǥ��뤿��˳����Ǥν����ᤫ�ä��ꡢ�������䤹���ä��ꤹ��Τ���ħ�Ǥ��������ʤ�250cc��400cc�˾����⡢125cc�Х����ǻ����褦�ʴ��Ф�Ĥ���Ǥ����괹���Ƥ�褤�Ǥ��礦��
�����Ǥ⥹�ԡ��ɴ���ڤ����
50cc���դ�30km��h���¤�����ޤ��������Ԥ�125cc���ȼ���®�����¤��ʤ����ᡢ�֤��緿�Х����ʤɤ�Ʊ���롼�������ޤ������Τ��ᡢ50cc���եХ�������٤ƥ��ԡ��ɴ���ڤ����Τ���ħ�Ǥ���
�ޤ��緿�Х����ξ�硢�����Ǥϥѥ�����ꤢ�ޤäƤ��ޤ���ǽ��ʬ�˳ڤ���Τ����Ǥ�����125cc�ǤϤ��礦���ɤ����ԡ��ɴ��DZ�ž��ڤ���ޤ���
����������ʬ�θ�ľ���ˤ��125cc�������եХ����Ȥʤä����ˤϡ�30km��h���¤���³����븫���ߤǤ���
���ʳ����ޤ�����
50cc�θ��դ�����θ����DZ��ޤ���ݤϡ�����ˤ������ä�2���ޤ�������ʳ����ޡפʤ���Фʤ�ޤ���
�����������Ԥ�125cc�����ʳ����ޤ�ɬ�פ��ʤ����֤�Ʊ��������ˡ�Ǹ������̲�Ǥ���Ȥ����㤤������ޤ���
����������ʬ�θ�ľ���ˤ��125cc�������եХ����Ȥʤä����ˤϡ����ʳ����ޤΥ롼�뤬�����Ѥ���븫���ߤǤ���
��;��Ǥ���
50cc�Ǥ���;�꤬�ػߤ���Ƥ��ޤ�����125cc�Ǥ��ȵ�����������ȵ�����դ���Ƥ���1ǯ�ʾ�вᤷ�Ƥ���С�����ƻ�ǤΥ���ǥ����ԡ���;��ˤ���ǽ�Ǥ���
�ޤȤ�
�Ķ����꤬����Ū�ˤ����ܤ����ʤ������ܤǤϡ�����2ǯ�ӽХ��������פλܹԤ�OBD������ܵ�̳���ˤ�ꡢ�Х������ӥ����˴ؤ��뵬���⸷�����ʤäƤ��ޤ���
OBD������ܵ�̳����Ŭ�Ѥ����ޤ�ͱͽ������ȤϤ�����Ŭ�Ѥ�����50cc���դβ��ʤ�⤯�ʤꡢ���ޤǤΤ褦�˵��ڤ˹������뤳�Ȥ����ʤ뤫�⤷��ޤ���
�������������Τʤ������ܤ�Ƥ���Τ�125cc�Х����Ǥ����淿���緿�ΥХ�������Ӥ������β��ʤ�ݻ��¤����ڤ��Ƽ����䤹���Ȥ��ä�̥�Ϥ�����ޤ���
����50cc�θ��եХ����˾�äƤ������ϡ����ε����125cc�Х����ؤ��㤤�ؤ���Ƥ���Ƥߤ�Τ��ɤ��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
�ܵ����ϡ�2024ǯ1��5�������ξ���Ǥ����������Ƥμ»ܤϡ������Ȥ���Ǥ�Τ�Ȱ�������ͭ�������θ���Ƥ����Ѥ��������褦���ꤤ�פ��ޤ���
�ǿ���������
-
�Х�����ݻ����� 2025.10.06 up �Х�����Ĺ���ݴɤ�����ˡ����ǯ���10ǯ�ݴɻ����������Ⱥƻ�ư���Υ����å����ܤ�Ҳ�
-
�Х�����ݻ����� 2025.10.06 up �Х����μָ��ϲ����������顩���ݤ��Υ��åȤ����ѤʤɥХ����ָ��δ��ܤ����
-
�Х������ 2025.10.06 up �Х����ν����ʤ������顩��Ѥ�ɬ�פʽ����ʶ�����κ�ȯ����ˡ
-
�Х������ 2025.10.06 up YAMAHA SR400����äƸ������äƸ��������ͳ�ϡ����Τ�̥�ϤȲ��ʹ�ƭ���طʤ���⡪
-
�Х������ 2025.09.19 up ��֥�250����äƸ�����롩��֥�250���͵�����ͳ�������ʤ�����Υݥ���Ȥ�Ҳ�
- ��äȸ���