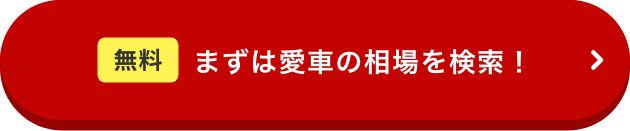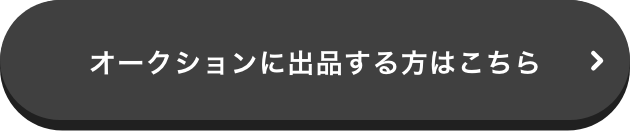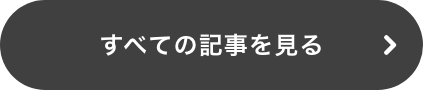バイク買取のチラシを貼るのは違法?対処法や注意すべきポイントを解説
目次
[
− 閉じる
]
自分のバイクに知らない業者のチラシが貼られていたというような経験をしたことはないでしょうか。高額な買取価格が並び、一見すると魅力的にも見えますが、実はその裏に思わぬ危険が潜んでいるかもしれません。
この記事では、バイク買取のチラシが貼られる背景や違法性の有無、悪質なケースの見分け方、そして実際にチラシが貼られた際の対処法までわかりやすく解説します。
勝手に貼られる買取チラシに不安を感じているなら、信頼できる方法で売却を考えてみませんか。
「グーバイク買取」なら専門のスタッフが出品から引き渡しまで徹底サポートします。査定後の営業電話は一切なく、オンラインでオークションへの出品が可能です。愛車の相場検索もスマートフォンから無料でできますので、お気軽にお試しください。
バイク買取チラシの実態
バイク買取チラシを貼るという行為自体は、違法なわけではありません。しかし、バイクに貼ったことでバイクに傷が付くなどした場合は器物破損、チラシを貼るために住宅の敷地内に勝手に入った場合は、住居侵入罪に該当する可能性があります。
ほかにも危険が多く潜むバイク買取チラシについて、特徴やトラブル事例の一端をご紹介します。
典型的なバイク買取チラシの特徴
バイク買取チラシのなかには、一般的な相場を大きく上回る買取金額を提示しているものや、「書類なしOK」「完全無料」など、極端な表現を多用しているものがあります。一見すると「お得な買取」だと思いがちですが、注意が必要です。
こうしたチラシには、実際には存在しない住所が記載されていたり、確認が困難な古物商許可番号が書かれていたりするケースもあります。
偽バイクセンターの問題
さらに厄介なのが、実在する有名な買取業者の名前を騙った「偽チラシ」の存在です。公式のロゴや名称を巧妙に模倣し、まるで本物のように見せかけているものもあります。
このようなチラシの真偽を見極めるには、公式サイトで情報を照合することが重要です。古物商許可番号は公安委員会のデータベースで確認できるため、必ずチェックするようにしましょう。
また、連絡先がフリーメールアドレスやLINEのIDのみといった場合は、特に警戒が必要です。正式な企業であれば、会社のドメインを使ったメールアドレスや固定電話の記載があるのが通常です。
窃盗団によるマーキングの可能性
バイク買取チラシには、もう1つ見逃せないリスクがあります。それは「窃盗団によるマーキング」として使われている可能性です。
特定のバイクにチラシを貼り、剥がされるまでの時間を計ることで乗る頻度などの情報を収集し、盗難のターゲットを選定していることも考えられます。つまり、チラシはただの営業手段ではなく、あなたの愛車が狙われているサインかもしれません。
バイク買取チラシが貼られたときの対処法

自分のバイクに買取チラシが貼られていたら、焦らず迅速に対応することが重要です。ここでは、適切な対処方法とやってはいけないNG行動について解説します。
すぐに剥がす
チラシを見つけた場合は放置せず、すぐに剥がすことが重要です。そのままにしておくとバイクが管理されていないと判断され、窃盗の標的にされるリスクが高まります。
チラシを剥がす際は、塗装まで剥がれてしまわないよう丁寧に行ないましょう。粘着の強いテープなどが使われている場合は、水で湿らせてからゆっくりと剥がすと傷みを抑えられます。
記載されている連絡先に連絡しない
記載されている電話番号やLINEのID、QRコードなどには、安易に連絡してはいけません。悪質な業者であった場合、個人情報を収集されたり、しつこい営業を受けたりする原因になります。
仮に本当にバイクの買取を実施していたとしても、言いがかりを付けて査定額を過剰に低くされる可能性があります。絶対にコンタクトを取らないようにしましょう。
有効なチラシ対策
チラシを貼られること自体を防ぐには、保管場所の見直しが効果的です。ガレージなどセキュリティの高い屋内や監視の目が届く場所、人目に付きにくい場所に保管するようにしましょう。
屋外保管の場合は、センサーライトや防犯カメラの設置によって不審者への牽制が可能です。防犯意識が高いことを示すだけでも、十分な抑止力になります。
バイクの安全な管理方法

チラシ対策に加えて、日常的な盗難防止策を講じておくことが、愛車を守るうえでは欠かせません。ここでは、基本的な防犯対策からおすすめのセキュリティグッズまでご紹介します。
バイクロック
防犯の基本となるのが、物理的なロックの活用です。バイクを停めるときは、U字ロックやディスクロック、チェーンロック、ワイヤーロックなどを使用し、バイクを動かせないよう固定しておきましょう。用途に応じた製品を使い分けると効果的です。
特におすすめなのが、複数のロックを併用する方法です。2つ以上を組み合わせることで、視覚的にも大きな抑止力となります。
また、ロックの取り付け位置や使い方にも注意しましょう。ホイールやハンドルに設置したり、駐車場の固定物を巻き込んで施錠したりするなど、正しい使い方で施錠することがポイントです。
バイクカバー
バイクカバーも防犯対策に有効です。外観を隠すことで、バイクの車種や価値を判断されにくくなります。
バイクカバーのなかには、ロック用の穴が付いているタイプや、アラームとセットで販売されているタイプもあります。物理的・視覚的に盗難を防ぐ効果があるため、積極的に活用しましょう。
おすすめのセキュリティグッズ
防犯対策は、ロックやカバーだけにとどまりません。近年では、万が一の際にバイクの位置を追跡できるよう、GPSトラッカーを取り付けている方も増えています。
そのほか、振動を検知すると音で警告するアラームや、エンジンをかけられなくするイモビライザーなど、多様なアイテムがあります。目的や使用環境に応じて、最適なグッズを選びましょう。
盗難被害に遭った場合の対処法
万が一、バイクが盗難に遭ってしまった場合には、速やかに適切な対応を取ることが重要です。ここでは、被害発覚後に取るべき行動を具体的に解説します。
警察へ被害届を出す
最初に行なうべきことは、警察への盗難届の提出です。届け出の際には、車種や年式、カラー、ナンバー、車体番号などの情報が必要になります。
届け出が受理されたら、受理番号を控えておきましょう。後日、保険会社や行政手続きで必要になることがあります。
また、防犯登録を行なっている場合は、その情報も忘れずに伝えるようにしてください。
行政手続きを行なう
バイクが盗まれてしまった場合、廃車手続きや一時抹消登録などの行政処理も必要になります。これは、税金の請求を止めるためと、盗まれたバイクが犯罪や事故に使われてしまった際、自分がその責任を問われることを避けるために行なう手続きです。
なお、手続きには警察に盗難届を提出した際の受理番号が必要となります。また、排気量ごとに必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
盗難保険の活用と保険金請求を行なう
盗難保険に加入している場合は、速やかに保険会社に連絡を取り、保険金請求の手続きを進めましょう。
その際、盗難届の受理番号をはじめ、バイクの購入証明書や車検証などの書類が必要になります。通常、調査には1ヵ月ほどかかり、そのあと、契約内容に応じた保険金が支払われます。
なお、請求から支払いまでの期間は30日以内が一般的です。
また、保険金請求は、警察への盗難届の提出と車両の抹消手続きが条件となるため、その2つを済ませてから依頼するようにしましょう。
まとめ
バイク買取チラシは、トラブルや盗難のリスクにつながるケースがあります。貼られた際は、高額買取や派手な表現に惑わされず、冷静な目で判断し、すぐに剥がすなどの対処を心がけましょう。
また、日常的な防犯対策を強化することで、盗難そのものを未然に防ぐことが可能です。万が一の際にも落ち着いて対応できるよう、必要な知識を習得し備えておきましょう。
愛車の売却を検討中の方は、しっかり査定して高値で取引できるサービスを選ぶことが大切です。
「グーバイク買取」は2,100社以上の業者が参加するオークション形式のため、高値での売却が期待できます。入札後の交渉も事務局がすべて対応しますので、安心して取引が進められます。まずはお気軽に無料の相場検索をお試しください。