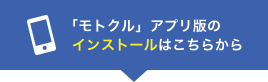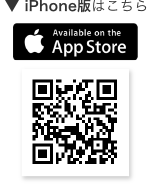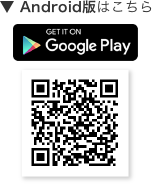GEN
▼所有車種
-
- GSX-R1000/R
1991 中型自動二輪免許取得
2023 モトクル開始
2024 大型自動二輪免許
バイク歴(うち16年間降車)
・スティード400
・SR400(2H6、1978、ドラム、ナロータンク、VMキャブ、トラッカー仕様)
・SR400SP(2H6、1985、大八車、Fディスク)
・SR400(1JR、1988、CVキャブ、フルペイトン、ロッカーズ)
・GPZ400R(ZX400D、1988、53馬力、ドラッグ仕様
・TZR250(1KT、3MA)
・RD250(352型)×3台
・バンバン90、GT80
・ninja400(ex400FFF)
現在、GSX-R1000(K1)、マグザム250(SG21)



球体バッフルの計画
賛否あるだろうが、自分は過去から、まず社外サイレンサーやマフラー、チャンバーへ交換している。しかしながら、現状の生活において、有名メーカーの製品は、カッコいいとは思っても、高級で手が出ない。
よって、ほとんど中華製。製品に精度、性能は求めず、自力で出来る改善を加える。よく言えば再設計と見直しだ。
今回、球体バッフルを着けようと考えたのは、消音性能の改善だ。
朝活が多い自分の習慣に合わせ、近隣からクレームが来る前に改善している姿勢を示したいのだ。現に出発前の停車断機は無くし、走りながらに変更した。
消音対策には、後付けのバッフルが一番簡単だと思う。サイレンサー本体に手を加えないのは、気に入っており、加工したくないからだ。
一般的に後付けバッフルは、中間パイプ付近に着けるインナー装着と、排気出口に着けるエンド装着があると言う認識だ。
インナー、エンドは、どちらも遮蔽や吸収を原理とする物理的な消音が多いと思う。
これらは、排気ガスを遮ることで消音する。
最近は、アクチュエータ作動によりON-OFFさせる後付けのバタフライ弁もあるが、これらは、構造上、消音出来る一方で抜けが悪くなる認識だ。(純正の排気デバイスは制御しているので別)
そこで、球体バッフルの発想である。球体は、流体を直径分の断面積で遮る一方で、外殻後方に回折する特性がある。流体力学の見聞によれば、球体を回折した流体は、直線で動くときと比較し、1.5倍の流速になるとのこと。球体の利点は、遮ると同時に、流速を稼ぎ、バッフルに採用すれば、消音と抜けが同時に得られることとなる。
実際、chat GPTとCopilotは、「世の中にこの構造を用いた製品は、あまりない」と語尾を濁したものの、その理由として、①球体は製造コストが高い(旋盤加工・高精度が必要)、②排気流設計や強度・耐熱など実装コストがささむ、ただしその分、音波回折・反射の特性が優れていることは、理論・実験双方で示されています。とのことだった。
あくまで理屈だが、経験知と情報を基にAIに何度も更問いを繰り返した整理だ。まずは試行してみようと思う。