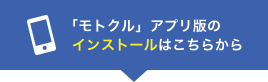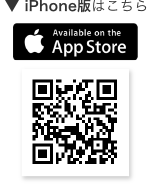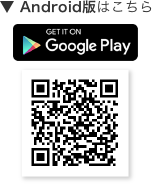T
北海道に住んでいます。
バイクブームだった80年代に青春を過ごしたおかげで、DNAレベルにバイク愛が刷り込まれました。16才の細胞に流れ込んだままです。
僕の人生はRZ50て始まり、GPZ900Rによって方向付けされました。それは、いまだに続いているようです。
直列4気筒エンジン以外にバイクの価値を見出せない男だと思っていたのですが、癖のあるVツインに乗り出したのは自分でも驚きです(歳かな?)
Kawasaki信者ですが、カワサキオンリーという訳ではないのです。
バイク歴
RZ50
GSX250S刀
CB400SF
ZZ-R400
GPZ900R(現)
ZX-11
スポーツスターXL1200S
K1200R
ZRX1200R(現)
Z900RS
V7Special(現)
よろしくお願いします。



8月10日早朝
市内はものすごい濃霧だったのですが、一歩市外へ出ると良い天気でした。
就実の丘で写真を撮っていると、老人といってよい年配の男性に話しかけられ、少し話しこみました。
老人いわく、「就実の丘は明治天皇の命名によるものだよ」と。
それは違うよ。と、思ったのですが、気持ちの良い朝に議論する事もないだろうと思い、それは知りませんでしたね〜。と、返しておきました。
明治天皇が命名。正解は、当たらずとも遠からず、といったところなのですが‥。
※ここから地域のマニア情報です。興味のある人はどうぞ読んでくださいませ。
就実の丘の通称が付いた経緯は下のようなものだと思います。
まず、老人の論拠は、
・明治期に天皇(明治天皇)が北海道を巡幸している。
・旭川に、離宮(皇居の別荘のようなもの)計画があった。
大きくはこの二つのようですが、明治14年の北海道巡幸時はまだこの辺りは未開の地と言っていい環境であり、天皇の巡幸経路も小樽、札幌、室蘭、函館と、道南〜道央に限られています。
確かに明治中期、上川離宮計画が持ち上がりますが、札幌その他の地区からの圧力がひどく、頓挫した経緯があります。
皇族の巡幸としては、明治の終わりに時の皇太子(大正天皇)が初めて旭川の地を訪れており、離宮予定地であった現上川神社を視察していますが、それだけです。
その他、明治天皇と旭川の関わりは、永山村(現旭川市永山地区)の命名くらいです。
では、就実の丘の「就実」とは何か?
おそらく明治41年に発表された詔書の一文によるものと思われます。
曰く「華を去り実に就き」→去華就実
日清日露戦争後、明治30年代に日本は空前の好景気となりました。また、これは世の常でありますが、勝った側には驕りが生まれるものです。
明治41年に発表された詔書(天皇が国民に向けて発する重要文書)とは、慢心した国民に向けた注意喚起のようなものであり、人間の本質にたちかえり質素に堅実に生きよ、というものであったようです。
就実の丘の命名は、ある写真家と言われており、この辺り一帯が御領地だった事、上川離宮予定地、陸軍第7師団などの関連、それらを含めた上で、この詔から拝借したのでしょう。
それにしても、この去華就実という言葉。
元を正せば中国の古事に由来する言葉のようですが、現代の天皇や日本人に、このような言葉を使える教養に根差した奥ゆかしさが残っているのでしょうか?