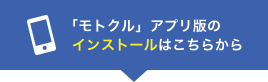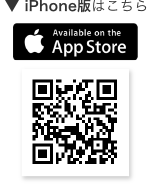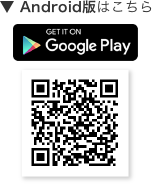山田うどん
武蔵国の川越出身でございます。
大和国がとても美しく、奈良の都へ憧れて…
「いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重に匂ひぬるかな」
「みかのはらわきて流るる泉河 いつみきとてか恋しかるらむ」
現在は山城国と大和国の国境付近に在住しております。





今ぞ知る みもすそ川の 御ながれ
波の下にも みやこありとは
壇ノ浦の戦いで安徳天皇と共に入水した二位尼・平時子の辞世の句です。
御裳川 と書いて 「みもすそ川」と読み、
伊勢神宮の境内を流れる五十鈴川の異名です。
安徳天皇は平清盛と時子の娘で平徳子(建礼門院)の子です。
わずか8歳で壇ノ浦の戦いで入水することになった幼帝・安徳天皇に、二位尼は「波の下にも都があるのですよ」と語り海に身を投げます。
山口県の下関の「みもすそ川公園」には二位尼(平時子)の辞世の句が刻まれています。
源義経が英雄のように語られることが多いのですが、源義経は戦争とは関係のない民間人を大量虐殺しており戦争犯罪人です。源義経は英雄ではないのです。
詳細は「判官びいき」の語源を調べて頂けると分かります。
現在、公園の中で源平合戦の紙芝居が絶賛上演中です。プログラムの内容は定期的に入れ替わるそうです。
紅白歌合戦や運動会の紅白帽は源平合戦の両軍の旗の色が由来になっています。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。
奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。
猛き者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵におなじ。
【現代語訳】
祇園精舎の鐘の音には諸行無常、すなわちこの世のすべての現象は絶えず変化していくものだという響きがある。
沙羅双樹の花の色は、どんなに勢いが盛んな者も必ず衰えるものであるという道理をあらわしている。
世に栄え得意になっている者も、その栄えはずっとは続かず、春の夜の夢のようである。
勢い盛んではげしい者も、結局は滅び去り、まるで風に吹き飛ばされる塵と同じようである。
『平家物語』第一巻「祇園精舎」より